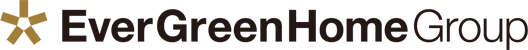暮れから年明けにかけて、我が家は発熱患者が後を絶たないような状況でした。聞くところによるとそうした家庭は多かったようです。インフルだコロナだマイコプラズマだと、雑多な輩が家庭に侵入してくる時代。防いでも防いでも堂々巡りは終わりません。
堂々巡り、といえば、建築業界の経済構造というのもまた堂々巡りです。先日ある知人からこんな話を聞きました。
ゼネコンが着手する規模の商業ビルのプロジェクト、そこにももちろんB工事の一つである空調設備工事が入ります。その工事価格が、ゼネコンに対してこれまでの2倍の見積りで提示されました。空調設備業者との値下げ交渉の余地はなかったそうです。つまり、相手が大手のゼネコンであったとしても引き下がる必要がないほど、2倍の価格であっても需要は引く手あまたである、ということです。だからといってゼネコンとしてはその跳ね上がりをそのまま入居者の負担に置き換えることはできません。そんなことをしたら入居が破談になってしまうからです。やむなくゼネコンは値上がり負担分を自らが被ったということです。
私が実感する上では、メディアが公言するほど人々の賃金は上がっていないはずです。世に言われる賃上げ上昇と、実際に現場で働く人達が得ている報酬の値上がり分、その理解に大きな乖離があります。そして資材価格の高騰も似たような構造なのではないでしょうか。そうしたいびつな経済構造であっても、必要な人は買う、買う人がいるのだから値を下げる必要なない、の堂々巡り。値下げのチキンレースというのはよく聞きますが、これでは値上げのチキンレースです。現場で働く人の報酬は言うほど潤っていないまま、資材値上げのチキンレースは一体いつまで続く…。
そうした状況の中の2025年、エバーは堅実な経営を維持しつつ今年30周年を迎えます。これまで創業者である私が支えてきたゆえに、「エバー」=「私」、でした。しかしこれからは「エバー」=「エバー」となり、私は私でこれまでのアイコン的な人物像から脱皮しないとなりません。若いスタッフでは太刀打ちのできない経験や見識を持ったお客様と釣り合う唯一の存在として、存在意義を存分に発揮することになります。それが「エバー」=「エバー」という新しい組織での私の立ち位置になってゆくのでしょう。