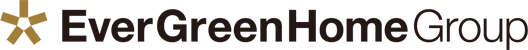前回のコラムで紹介した茅ケ崎美術館での「美術館建築 ― アートと建築が包み合うとき」という展示は素晴らしいものでした。今回はその延長線上となり、できれば前回のコラムと合わせてご一読いただければと思います。今回はその展示の出展者であり著名な建築家である坂茂(ばん しげる)さんのお話をさせていただきます。
(そんな坂さんですが、つい数日前、手がけた銀座の商業ビルのエレベーターが不具合を起こしニュースとなりました。幸い誰も怪我などせず済んだようです。氏の志を知る者としては、建築家が悪いとばかりにその情報をねちねちこねくり回す報道やSNSというのはどうかと思います…)
坂さんは、「志」の人です。
ポンピドゥーセンターをはじめとする世界の有名な建築物を手がけ、プリツカー賞や紫綬褒章などそうそうたる受賞歴を誇る氏ですが、そのような華々しい表舞台の仕事に携わるかたわら、被災地の仮設住宅建設を主とした支援活動に心血を注いでいます。
その有名なアイテムが紙管(紙の筒)です。ことの発端はとある展覧会の会場構成で「1カ月ほどの展覧会に貴重な木を使ってゴミにするのが嫌だった」という思いでした。そこで木より安い材料を探し、何度も試験を重ね紙管にたどり着いたといいます。バブルの時代のことで、エコロジーとか環境問題とかが取り沙汰されるもっと前のことです。
紙管が良いのは世界中のどこでも手に入り、何度でもリサイクルできることです。環境ブームで木を使うことが流行っている今も「考えなしに木を仮設で使うべきじゃない」と氏は言います。木は大切な材料なのだ、と。
氏は1995年の阪神・淡路大震災以来、数々の被災地に赴き、その惨状を目の当たりにし、仮設住宅の在り方というものを模索されてきました。考案された紙の間仕切り(パーティション)システムもその一つ。紙管を活用し、そこに布を渡して被災者のプライバシーを守りつつ、同時に完全な密閉ではない分被災者の健康管理ができるというものです。コロナの時には飛沫感染の防止にも役立ちました。その発想は常に「仮設なのだから必要以上のコストや資源を費やすことはない。しかしそこに暮らす人々が快適でなければ意味がない」というものです。
建築家というと、歴史が物語るように、権威ある者がそれを誇示するために贅沢で巨大な施設やモニュメントを創造する役割でした。けれども坂さんはそこに矛盾を感じていました。建築って、建築家って、そういうものなのだろうか?と。
国内にとどまらず氏の支援活動は、アフリカのルワンダ難民のためやベトナム難民のためなど、ありとあらゆる国で困っている人々のために行われています。紙管は世界のどこでも容易に調達できる安価な材料です。自然災害や戦争が起きると建築資材が値上がりします。その影響を受けにくい材料を使い、プロに頼まなくても素人が組み立てられる住宅が必要だ、と考えてきました。紙管の建物や紙の間仕切りシステムは、今や能登半島で、戦禍のウクライナで、世界中で、役立っています。
坂さんは「人は建築で死ぬ」と言っています。人は地震で死ぬんじゃなく、建物が崩れることで死ぬのだ、と。
再々に私がコラムで触れている、年々厳しさの増す耐震等級についてのやるせない思いを、この言葉はシンプルに言い表しているように感じます。家は未来永劫に使うものではなく、その時代時代で必要とする人が使うものに過ぎない。それは言い換えれば仮設住宅と同義である。仮設を長く利用すれば恒久になる、だから仮設と恒久は紙一重なのだ。建築家はその仮設住宅を未来に向けて意義あるものとして考えなければならない。それが建築家の社会貢献である、と。
私は、同じ建築に携わる者のはしくれとして、氏の志に頭が下がります。
家は、右へならえ的な画一的なスペックを満たすために、高価に、複雑に、なって欲しくない、と思うのです。