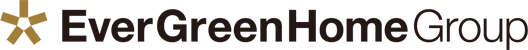百人の人間がいれば、百人の考え方があるのだと思います。まったく同じ考え方の人などいるはずもありません。しかし、それでも共通すべき考え方や思いというものは必要で、それがいわゆる「常識」というものです。常識を感じることができ、自己を主張するだけでなく、他者を許容することのできる、協調的なバランスをもった人を「常識的な人間」と呼ぶのだと思います。世の中は、常識的なルールを共有することで成り立っています。他人の喜びを自分の喜びのように感じる能力や、自分の痛みを他人が察してくれるような能力、そういった素晴らしい感性が、そこに生まれてくるものです。
ところが、それを持たない人々というのもいます。彼らは共有すべき常識とは異なる要因を心に持ち続けています。どうしてそのようなことが起こるかといえば、百人いれば百の生い立ちがあり、百の境遇があったわけで、その中で必要な意識が欠如するのは仕方のないことです。それは本人が招いた場合もあるし、本人のせいでない場合もあります。
たとえて言えば「ナッツ姫」です。世襲の色濃い国に生まれて御姫様のように扱われて、意見の違う人間が登場したらすぐさま周囲の力を利用して消すことができました。自分の意のままにならないことなどないのだと生きてきた彼女に「常識的になれ」と言ったところで、「なんで?どうしてあなた方と同じにしなければならないの?」という答えしか返ってこないのでしょう。これはもっともなことだと思います。ある一定以上の力を持った人間には、大方の人が持っている常識は、あてはめる必要がない時がよくあるからです。
しかし、それが問題となった時に、ようやく本人は「常識的な人間」ではなかった、と気づかされます。悲劇なのは、自らが気づくのではなく、周囲の反応から気づかされるのです。その時点でも、未だに自分は悪くないのだと思っている人も多いと思います。それはどうしてかというと、今までその人は、そのやり方でしか生きて来なかったし、それで通用してきたからです。充分な成功をしたし、ほかの誰かに足並みを合わせることなど必要がなかったからです。
また、元プロ野球選手のこんなエピソードがあります。彼は子供の頃からその才能を周囲に認められ、言わば一般の部員とは異なる特権階級でした。まさに特別扱いで、チームメイトの誰もがしてきた用具の後片付けやグラウンドの整備などは一切せず、また自分もそういう扱いを受けることを当然だと考えていました。そしてプロの道に行き、ある程度の活躍をして引退をするわけですが、特権階級におさまっていた野球の世界から去って後、彼には何もなくなっていました。彼から野球を取った時に、彼に残っていたものは、誰一人として共有することのできない、彼だけが持っていた王様の価値観だけだったからです。
例えに出した「ナッツ姫」さんには申し訳ないのですが、環境や風貌や違えど、彼女のように協調して常識を育むことができなかった人というのは、大なり小なり、私たちの日々の周囲に多く存在しています。わざわざ思い出そうと努力しなくても「あの人ほんと身勝手だよなあ…」と感じる人が、パッと何人か浮かぶことと思います。
彼らは、いつか協調的で常識的な世界へやって来ることができるのでしょうか?やって来ることができるとしたなら、失敗したり、挫折したりした時に、いかに現実を(自分を)直視できるかどうかにかかっているのだと思います。自分と自分以外の人々と、どこが違っていたのかを、真摯に直面できる本当に数少ないチャンスです。「それでも私は間違っていない」と言ってしまうのだとしたら、それは残念としか言いようかありません。