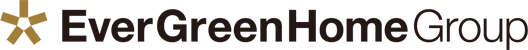マツダがすごい車のエンジンを開発したそうです。
読み知るところによると、リッター当り約30キロ走る画期的な低燃費エンジンであると。シェアの大半を占める低トルク車のエンジン開発に非常に大きな一石を投じたことになります。マツダはかつてもロータリーエンジンという自社独自の開発エンジンを市場に送り込んだ輝かしい歴史があります。信じた我が道をゆく技術者精神というものがそこに息づいているように思えました。今回はそこに社内事情も手伝ったようです。マツダは密接な関係を持つアメリカのフォード社からハイブリッドエンジンを購入せざるを得ないことから、自社内での独自的なハイブリッドエンジンの開発は行えなかったそうです。しかし、それが逆に功を奏し、全く新しいスタイルのエンジンが生まれた要因にもなったということ。しかし、やはりそこには社風というか、ロータリーエンジンを彷彿するような根本を見据える議論がなされたからなのでは、と感じます。業界全体がハイブリッドエンジンの限界力のアップや付加価値探しに時間と労力を費やす中で、マツダという会社はトレンドに流されることなくエンジンというものの根本部分の見直しを進めていたわけです。
全てにおいて「根本を見直す」という行為は必要なことです。それは言葉を換えて「原点に帰る」とも言われます。マツダのように、エンジンという根本から見直していくこと、それが周囲の出来事全体を根本から良い方向に持っていきます。世の中の動きに乗ることだけを考えて、事の発端(原点)を考えないで済ましていると、当然ですが根本的に良くなんかなりません。
根本を見直せる人とは、どんな人でしょう?
私は、逆境にいる人や、逆境を知っている人ではないかと思います。窮地にいる中で一つの信念を見出そうと必死になって、やっと見つけた信念は貫くまでやり通すしかない人です。仮にその人に頼るべき資本があったなら、たとえ窮地に立たされてもその資本が救ってくれるかもしれません。だから、お金なんかない方が、人は何かを成すのではないかと、私は思います。
私の仕事でいうなら、根本を見直すということは、お客様の声に常に立ち帰るということです。「猪狩はまたずいぶん格好いいこと言って」とお思いになるかもしれませんが、広告を行わないエバーがどうやって生き残っていくか、それはお客様個々の評価と、その評価がまた別の誰かに広まっていくよ効果からでしか導き出されないものであるからです。売上げの数字のようなものは二の次です。まず満足していただく家をつくる、それが一番でなければ、エバーという会社はたちどころに消えてしまうのかもしれません。
マツダのニュースが個人的にやけに心に残ったのは、決して気を抜いてはいけない自分の立場を、あらためて実感させられたからなのかもしれません。
先日、エバーの営業のHが、私のことを他人にこう話していたそうです。「うちの社長は、ほかの会社の社長みたいに接待やらゴルフやらで会社を空けたりしないし、ほかの会社の社長がしないような現場廻りを毎日のようにやっている。とても“まとも”だと思う。」・・・苦笑。
そうか、とりあえずスタッフからは“まとも”に見られているわけか。少しは安堵しましたが、それ以上に恥ずかしい気分になりました。Hよ、頼むから、これ以上外部には変な褒め方をしないでくれ。