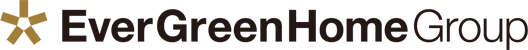同じ鉄砲道沿いの老李(ラオ・リー/LAO-LI)さんに食事に行きました。老李さんはエバーが2008年に建てたRC造のモダンな中華料理店。店内は広々として気持ちよく、料理は抜群、おすすめのお店です。
しかし今ではこの建物はつくることができません。高度な断熱性能というものが建築基準となりました。エネルギーの消費を抑制するエコな性能の断熱は、断熱材を主として日増しに使用基準が厳しくなり、2022年に新たに制定された内容では、断熱等級は5から7というのが「新基準」となりました。今年建ててよい家の断熱基準の4は、すでに最低基準となり、2030年になると断熱基準4の家は建築不可となります。
つまり、2021年までは最高基準だった断熱等級4の建物が、10年も経たないうちに、建ててはいけないレベル、になっていくのです。余りにもいとまのない見直しです。さらには気の早い広告は「今から建てる家は断熱等級6が新常識!」と煽り始めました。まるで「そうじゃないとこれからはキケン!」とばかりに強迫します。
エバーはその時その時の法令や基準を遵守して家を建てます。しかし、一方でそれら過剰スペックが多々あることも認識しています。私と同感の同業者は非常に多いです。皆が、その変更が後々に十分な検証を行わないものだと、半ばあきらめの気持ちでいます。
さて、老李さんですが、冬といえども断熱材を入れない打ち放しの店内であっても実に快適です。欠点を無理やり見つけるなら、壁沿いはコンクリートの冷えで多少は室温が下がることもあるでしょう。そうだとしても室内の暖房は気配りをもって循環しており、何の不快もありません。断熱至上主義を追求するのは、日常生活から生きる知恵や工夫をする楽しさを奪う、とも言えます。
断熱等級が上がるというのは断熱材だけの問題ではなく、サッシのつくりや壁材の重厚化などあらゆる部材に関わっていきます。ゆえに普通に考えれば、断熱等級が上がるほどその家の解体時に出る廃材の量や種類も増えていきます。それが果たしてエコなのか?いつかラオリーさんを解体する時がきたら、その時に出るのは鉄骨、鉄筋と砕かれたコンクリート。どれも再生可能なアイテムだけです。まさにエコな建物です。
ルールだけ作って、それで満足して、また時が来たらそのルールを過剰に書き換えて、またそれでいったん満足して…その繰り返しです。事後の検証というものがありません。必要だったか、そうでなかったか、きちんと検証していけば、何が大げさな基準なのか、審査なのか、そういったことも判明するはずです。基準や審査のレベルアップは十分な検証とともに必要最低限にして、むしろそれに違反した場合の罰則を強化した方が将来のためになる、と私は思うのですが。
200年住宅なんていうものがありました。人間の寿命は限りがあるのに、どうして2割も建築コストが上がる家を建てなければならない?ISO(工業製品の国際標準)取得というのも一時は盛り上がりました。結局はマニュアルに縛られ改善に振り回される始末。単に認証を得たいだけだったりも。どちらもいつの間にか聞かれなくなりました。どこに行っちゃったんでしょうね。きちんと検証をして白黒をつけるべきだったのではないでしょうか。
大船渡の山火事が雨で沈下した時、一瞬にしてテレビは報道を終えました。もういいか、と思ったのでしょうね。しかし大事なことは、どうしてあのようなことになったのか?自然災害なのか人災なのか?防ぐにはどうすれば、なったらどうすればいいか?という、未来のための原因究明と対策を話し合わなければならないのに、派手な映像を撮り終えたら「はい終了~」です。
私はまたもテレビに突っ込みます。「おいおい、検証はどうした?」