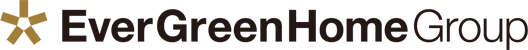若い頃に見ていいと思った建築は、いま見てもいい建築だと感じます。
まっ先に思い出すのは、東海岸北に今もある某建築設計事務所の建物。それは1983年、まだ学生だった私の目の前に現われました。曲線の屋根をもつ鉄骨造のモダンなデザイン。上品な遊び心と機能性を感じる正方形や円形や三角形の窓。明らかに周囲の家々とは違っていました。当時感じた斬新さは、30余年経た今では特別なものではないかもしれません。それでも、今でも学生の頃に感じたのと同じように、そこを通る毎に「いい建物だな」と思います。
考えてみれば、既製品や規格品といった「有り物」を使うことで家のコストを下げられるような、今日のような時代ではありませんでした。
家をつくるのに財を費やせる人は、設計であれ機能であれディテールであれ明らかに一般庶民とは違う発想で家づくりができたわけです。「他とは違う」と感じるのは当たり前です。既製品や規格品ばかりでなく、技術や設計といったことも含めてあらゆるものが合理化され、より多くの人が家づくりを「楽しめる」ような今ですが、その反面 、寂しいことも感じます。
最近、家づくりの雑誌などをパラパラとめくっていて、「何だかどの家も同じだなあ」と思ってしまうのです。
一見個性いろいろでも、私にとって同じ家に見えてしまうのは、既存の概念にちょこっと味付けをするくらいのレベルでしか家づくりを考えていないような気がするからです。
「どうですこのコンセプト。このデザイン。他ではできないですよ。」とは大袈裟に言うけれど、見識のある人間からすれば、それが家づくりの本質なのかどうかは疑わしいものがあります。お施主のことを親身に考えて「これなら喜ばれる、これは新しい」という発見が見つからないのです。
実際、専門誌でいま話題などと言われているコンセプトやデザインのほとんどが、一過性のトレンドのような気がしてなりません。魅力的な特徴を謳い上げているわりには、本当にお施主の方を向いて仕事をしているのか、疑問です。そんな見方だから、どれも同じ家に見えてしまいます。これはゼネラルメーカーの話ではなく、デザイナーやハウスビルダーの話です。
デザイナーやハウスビルダーへの依頼であっても、特徴付けや見た目に惑わされることなく、とことんつくり手の真価を見極めていかないと「結局のところ外観は新しい感じがしたけれど中身はがっかりした」とか「コンセプト通りだったけどそれ以外のことは平均点以下だった」とかいう結末に陥ることがあると申し上げておきます。
何かひとつの得意技に惹かれて依頼するのではなく、総合評価してバランス感覚の優れたつくり手に依頼するのがベストではないでしょうか。家はつくり手の言い分だけでもできないし、お施主様の言い分だけでも形になるものではありません。双方それぞれの良いところをバランスよく取り入れて、全体としてアベレージの高い家になることが理想ではないでしょうか。
昔から、そして今でもいいと思っている東海岸北の某建物は、ただその周囲との違いだけで私を惹きつけたわけではありません。要するに、全体としてバランスがいいのです。「やっつけ」や「なあなあ」や「思い込み」が少しも感じられないことが、とても嬉しいのです。