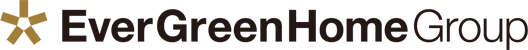自分の部屋から大麻疑惑の力士が出た直後だというのに、ふだんと変わることなくいつも通りサウナに出かける親方というのがいました。
ふだんとは明らかに違う状況にあっても、ふだんと同じ日常を過ごせる心境というのが私には理解できません。「自分に一大事が起きているのに、それをまるで他人事のように遠いものとして錯角している。現実をバーチャルとして捉えている」日曜の朝のテレビニュースで某コメンテイターがこう解説していました。
なるほど、そうやって最近の一連の非常識な事件を観てみると、役人の不祥事も、食品偽装も、どれも、当事者のコメントはどこか現実ではなく、“ひとごと”のように語っています。部屋を解雇された力士も力士でした。「警察は許したのになぜ協会は許してくれない?」的に開き直っていましたが、当事者本人が口に出す言葉とは思えませんでした。親友でもかばうかのような“ひとごと”な口ぶり。
“ひとごと”は、そうした対岸の出来事ではなく、私の周囲で感じています。
好景気の気配を感じないまま、建築業界は上場企業も含めて倒産する会社が後を断ちません。
ご承知の通り、そうした時にはまず銀行や投資家が資産回収を行います。会社を大きくしたのが彼らですから当然といえば当然ですが、損をするのは汗水たらしてがんばってきた下請け業者です。後回しにされた未払いの精算は、今までの人間関係、そして今後の付き合いのことなどいろいろあり、結局うやむやにせざるを得ないことも多々あります。当のつぶれた会社の経営者が、下請け業者と同じくらいに腹を痛めているかというと、実はそうでもなかったりして、とどのつまりは下請け業者のような、一生懸命にやっている下の者が馬鹿をみる、そんな社会構造になっています。
何かあった時に、痛みを分かち合う、という構造になっていない。実質的にトップの責任というのがひどく曖昧です。立場的に下の者が痛みを感じた時に、それを“ひとごと”として感じてもいい、といった社会構造になっているせいでもあります。
私は経営者ですが、あえてそうしたことを矛盾に感じたので、こうして書きました。
一生懸命にやっている者が馬鹿をみる世の中というのは、明らかに間違っているからです。責任をとらなくていい人間をつくる社会の仕組みそのものを変えていかないと、どんどん“ひとごと”は加速するのでは・・・