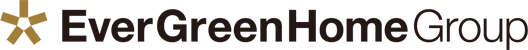知人の別宅である古民家が茅(かや)の葺き替えをおこなうというので、仕事の合間をぬって二宮の山中まで出かけた。
茅が家を雨から守り、通気を行い、暮らしを快適にしてきた。
その下で囲炉裏をかこんでは家族の絆を深め、立ち上る煙が茅に防虫をほどこす。
そして30年にいちどの葺き替えの時を迎え、また生まれ変わる。
リサイクルとは、まさにこれだと思う。
古民家の葺き替えを担える職人が少ないと言う。数年前に屋根の一部を葺き替えた時に頼んだ親方はすでに80才以上、その下で働く職人さんも若くて60才代であったらし い。親方は跡を継ぐ者がいないと嘆いていらしたそうだ。
職人さんもさることながら、まず、茅葺き用の茅さえ手に入らないのだと知人が教えてくれた。そして茅が手に入り職人さんを見つけたとしても、維持するためにかかる費用は相当な額になるらしい。住んでいる人が茅葺き屋根を維持したいと思った としても、金銭面で折り合わずやむなくトタンをかぶせてしまったり、かわら屋根にしたりというところも多いと聞く。かつてみんな茅葺きだったここの30軒の集落も今 はこの古民家が残るだけになってしまったとのこと。
それでも光はある。今回葺き替えをしている職人さん達は若く、20~40才代。数年前に設立された岩手県の茅葺き技 術の伝承を促進し、茅場を維持管理するNPOのメンバーなのだそうだ。このNPOを創設された方が先日葺き替えの様子を見にこられて、失われていく技術と風景を何とかして守らなければと決意した経緯や、茅葺き屋根の良さを熱っぽく語っていらしたと聞く。
素晴らしいことだと思う。
友人や近隣の人々が来て、力仕事ができるものは職人を手伝い、女性たちは柿を軒にぶら下げる。女性たちはお婆ちゃんに教わりながら、初めての経験に嬉々として時間を過ごす。軒は夏の直射日光をさえぎり、冬にはおだやかな傾光のもとで干し柿をつくる。軒とはそういうものなのだ。
現役のハウスビルダーでさえ、あらためてそのことを発見していることに驚く。ほんとうに必要な時間を過ごしているのだと実感。
茅葺きの古民家・実生庵について
今回の葺き替えしかり、多くの維持管理にコストがかかる昨今。当家では「茅葺き基金」なる善意の資金集めを個人で行っています。
また興味がお有りの方は日時の折合いがつく限り見学を歓迎しているとのことです。
- 茅葺き基金、見学等のお問い合せはこちらへ
- 実生庵オーナー 小田切 myon@af.airnet.ne.jp