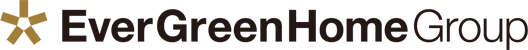新国立競技場のデザインが決まりましたね。蓋を開けたら、「和の大家」隈研吾氏と、同じく世界的建築家である伊東豊雄氏の一騎打ち、頂上決戦といった風でした。結果は僅差で隈さんに軍配が上がったわけですが、正直、今回は私、どちらに決まっても問題ないという印象でした。自転車のヘルメットみたいなザハ案よりはどちらもはるかに良いと思った次第です。しかし“木と緑の”新国立競技場なんて、期待する一方で、未知なる部分も多く、気になります。なんせそこに大勢の観客を招き入れるわけですからね。どんな構造をしているのでしょう。相当な強度が必要なはずです。経年で取り替えはきくのだろうか。今後の進展が期待されます。今回は前回に比べてよい勝負だったのではないでしょうか。
ただ、その後が残念でした。僅差で負けた側が、コンセプト、採点、デザイン等すべてに対して批判的な発言をしたのです。とりわけデザインについては「一見かたちは違うがザハ案と全く同じ」と、悪意あるコメントを残しました。そして共鳴するようにザハ側も「似ている」と言い出す始末。がっかりです。
この「がっかり」感は、建築家のはしくれとして、とか、専門的な観点から、という意味での「がっかり」とは違います。単に「みっともないなあ…」と思っただけです。何故って、「コンペ」はケンカではないからです。終わってからも相手を罵るものではありません。真摯に結果を受け入れるだけです。採用されるには採用されるなりの理由があり、採用されなかったのには採用されなかったなりの理由があった、それだけのことです。それなのに「そっちが採用されるのはおかしい!第一パクリじゃないか!」とがなりたてるなんて、実にみっともない。もしも明らかな模倣があったとしたら、第三者がそれを取り上げるならいいでしょう。しかし、それを負けた本人が言ったら、ただの負け惜しみにしか聞こえません。
人の度量というのは、負けた時に顕著にあらわれるようです。そういう時こそ、自分のいたらなさを素直に認めて、勝者を讃えるべきだと思います。第一、勝者にエールを送れない敗者なんて、「みっともない」の代表です。「本当は俺が作ったものの方が優れてるのに…」それは、仲のいい者達に囲まれた酒の席だけにしましょう。