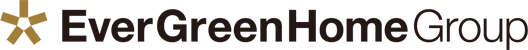6月8日まで茅ヶ崎市美術館で「美術館建築 ― アートと建築が包み合うとき」という展示をやっています。美術館建築を取り上げるという美術展は、東京でならいざ知らず、ここ茅ケ崎で行われるというのは貴重です。石見地方特産の石州瓦で建物全体を覆い釉薬の違いにより玉虫色の建築をつくり上げた内藤廣氏の「島根県芸術文化センター」。広島の造船技術を活用した可動展示室を中心に10棟のヴィラ・レストランからなる坂茂氏の「下瀬美術館」。瀬戸内の島につくられた銅製錬所の遺構を活用して自然エネルギーによる循環型建築をつくり出した三分一博志氏の「犬島精錬所美術館」。環境・アート・建築が一体となり上部に大きく開けた穴から移ろう自然を採り込む西沢立衛氏の「豊島美術館」。そしてここ、鳥が翼を広げたような屋根が特徴的な山口洋一郎氏による「茅ヶ崎市美術館」。こうした5つの珠玉の美術館建築を取り上げています。とても興味深い美術展なので興味がお有りでしたらぜひ足を運んでみることをおすすめします。
私は仕事の合間を見つけて内藤廣氏の講演を聞きました。島根県芸術文化センターの瓦というのは特別な耐火性をもったもので、本物と呼べる物を丹念に創造し取り入れることが建築の一つの本質、文化、というものを生み出しています。
私は最近、文化の持つ本当の価値と、付加価値との違いについてよく考えていました。付加価値とは何だろう?付加価値は必要なのか?そもそも付加価値は価値なのか?…
そんな時に氏の講演を聞く機会となり、氏の考える本当の価値を創造するアプローチに触れ、あらためて「不付価値ってなんだ?」と考えるようになりました。講演の終わりにぜひそのことについて氏に質問をしてみようと思っていたのですが、あいにく仕事に戻らなければならず、かないませんでした。氏がどう応えてくれただろうか、気になるところです。
建築とは悠久の時間がつくり出した文化であり、魂があり技術があります。そこには本当の価値があります。しかしながら現在は付加価値にがんじがらめになってしまっているように思えます。この4月に施行される建築基準法の改正は、建築物の構造や防火、省エネ基準などさまざまな点で見直しがされます。その精査で3週間あればできる住宅が2か月もかかってしまうようなことになっています。こうしたことは、文化としての建築が本来もっているべき価値とは異なるものばかりを膨張させているのではないか?だとすれば、私たちはそうした付加価値に翻弄されているのではないか?と私はどうしても考えてしまうのです。
いつの間にか、私たちが取り組んでいる家づくりは、付加価値に縛られて身動きが取れなくなっているように思えます。それって、家という文化の本当の価値から逸れて、どんどん間違った方向に進んでいる気がしてなりません。家だけではありません。私たちはいつしかあらゆる付加価値に翻弄されている毎日を送っている気がするのです。