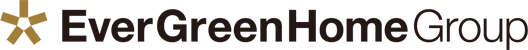日本語は、世界中の言語の中で最も難しい言葉だといわれています。「すみません」というのはある時には「申し訳ありません」だったり、ある時には「ちょっとよろしいですか?」だったり、ある時には「どうも恐縮です」だったり、一つの言葉でもいくつかの意味を持つのだから厄介です。私たちはふだんからこの使い分けを学習しているわけですが、言葉が多用な意味を持つということは多分に曖昧さを秘めているわけで、それがすなわち国民性のようにも思います。その点、英語のようなものは日本語ほど曖昧ではありません。抒情的でないから奥行きがないとも感じますが、日本語ほど誤解を与えることもありません。言葉を大切に使うことはとても重要です。ただ、だからといって言葉だけに依存することも危険です。ただ一方的に演説するだけならいいだけですが、私たちは会話をしなければならず、そこでは互いを理解し合うことが必要だからです。
先日ある人物との間でこんなやりとりがありました。
ー その人「このエバーのパンフレットどこに置いておきましょうか?」
ー 私「うーん…入口のこの辺りでいいんじゃない?」
ー その人「だけどこの辺りだと雨が降ったら濡れてしまうんです」
ー 私「あ、そう…じゃあ雨が降ったら中に入れればいいんじゃない?」
ー その人「はい、でも中にいると雨が降っても気づかないんです、どうしましょう?」
ー 私「…じゃあ別の場所に置いたら?」その人「でもさっき猪狩さん、この辺りに置いたら?って…」
ー 私「…」
そう、私、「この辺りに置いて」と指示を出したわけではないのです。なのにその人は「指示された」と受け取ったのです。そういうこと、私、いちいち細かいタイプではないし、その人がいいと思った場所に置けばそれでよかったわけです。まあ聞かれたから「ここらへんでいいんじゃない?」と言ったまでで、「ここらへん」じゃなくても別によそでもかまわないわけです。なんでしょう、このチグハグなコミュニケーション。言葉が足りないわけでも、言葉を誤って解釈されたわけでもないのですが、まるで噛み合っていませんでした。その人物と別れてから、私はこう思いました「あれ?なんか俺が悪かったことになってない?」(笑)。
この程度なら大したことにはなりません。しかしそれがお施主様とのやりとりとなったら、噛み合っていないことはそれはもう命取りになります。我々はよくお客様に「あとは任せます」と言われます。しかしこの言葉にも実はたくさんの異なる意味がこめられています。「ここから先の細かい話はいちいちチェックしてたら面倒なので任せます」という意味の時もあれば、「ここから先は挑戦も含めて貴方の手腕が見たいから任せます」という意味の時もあります。結局、そのどちらも完全に任されたわけではなく、必ずお施主様の了解が今後も必要になってくるので、実際は「任された」わけではないのです。それを言葉だけを鵜呑みにして、お施主様のことを理解していると過信して、「任された」という言葉だけを頼りにして勝手してしまうと、でき上がってからお施主様が「あれ?任せるとは言ったけど、何これ?」みたいになっては大変です。時すでに遅し、せっかくの信用もその時点で地に落ちます。
一流の医者というのは、素人には余計だと思われる質問や、病気とは無関係に思えるような質問をします。そしてその答えから隠れている原因や病を発見したりします。それは、患者のもつ言葉というのが万能ではない、という前提に立っているからです。私たちは難しい言語を操る日本人ですが、それでも言葉だけで互いを理解し合うことは難しい。そういう観点で、私たちは言葉にならない、言葉にできないお施主様の思いというのを理解していかないといけないと思っています。仕草、表情、間、性格、そういったものの中にある微かな意志を見逃さないようにしていこうと意識しています。