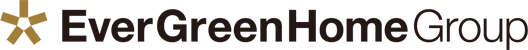「たくさん本を読むほど、賢くなれる。」
これ、皆さんはどうお思いになるでしょうね。「うん、確かにその通り」とお思いの方もいらっしゃるでしょう。しかし、私はあまりそうは思いません。要は、読書の「質」の問題ではないか、と私は思います。
私は、好きな本は何度も読みます。再び読むと、最初に読んだ時とは異なる感想を抱いたりします。3度目に読んでみると、今度は今までは引っかからなかった描写の優れた点や、主人公の微妙な感情の移り変わりや、作者の物語にこめた真意などが初めて理解できたりします。何度も読めば読むほど、その本を深く感じることができるようになります。上っ面の活字だけを追っていた最初の時とは違う感じ方ができている自分を、「まだまだ駄目だな」と反省したり、逆に「ここまで読み解けるようになった」と評価したりします。そのことの繰り返しが、自分という人間を少しずつ成長させているように思えます。
(そういえば、あの安藤忠雄氏は、本の気になった所に赤いラインを引くそうです。そしてしばらくしてから読み返した時に、その赤いラインを引いた所を見て、自分のかつての偏りや未熟さを実感するそうです。そして再度ラインを引く。3度目に読んだ時には、自分の成長の跡がさらに確認できるというわけです。好きな本をそのようにして活用するというのも、素敵だと思います。)
そうではなく、一度読んで、面白くて、「あー面白かった!」と放り投げて、もうその本のことはさっぱり忘れて、次の本に手を伸ばすような性格だったとしたら、私は、今の自分よりもっと未熟な人間だったと思います。「面白かったんだから、もう一度読んだら、もっと面白いはずだ」…これは、欲です。せっかく面白いものを見つけたというのに、その面白さを骨の髄までしゃぶらずに、次の何かを探しに出てしまうなんて、欲のない、つまらない人間がすることのように、思えてしまいます。だから、つまらない人間の観察力というのは、浅い(質が低い)んじゃないか?などと思ってしまいます。
私はスタッフの報告を、よく疑ってかかります。
「あのお客様、なんとおっしゃってた?」
「いいですよ、それで、と電話でおっしゃっていました」
私はそこで、そのお施主様のことをイメージしてみました。…あのお施主様は、満足した時にそういう言葉遣いはしないんじゃないか?むしろ、不満を残している時に、そういう口調になるような…?
後で私の方から当のお客様に確かめてみると、案の定、その言葉の真意は「この際、もうそれでいいや」的なものでした。そう、言葉だけで相手の真意を判断してはいけないのです。ふだんからそのお客様のことを理解しようと観察していれば、言葉だけで簡単に真に受けるようなことはしなくなることができます。うちのスタッフは優秀なのでそういうのはレアなケースなのですが、それでもやはり気をつけなければなりません。
読書も然り、仕事も然り、大切なのは、量よりもむしろ質のように思います。意味のないトレーニングを100時間やることは、そのトレーニングをやらせた人間が悪いです。しかし「その100時間を何の疑問も感じずにやっちゃったアナタも、同じくらい悪いんじゃない?」と私は言います。