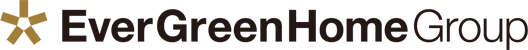相手に必要以上の不安を与えてしまうというのは、非常によくないことだと思います。
私たちのことで言えば、お客様の不安に一緒になって不安がってしまうことです。そこで黙ってしまおうものなら、それはもうそこで終わり。最悪です。正しい行いは、その不安感を前向きに検討しようとする気持ちと意思表示です。日を置いてでもいい、必ず何とかする、できる、と責任をもって応えられること。一緒になって不安がっていてはいけません。それはお客様をさらに不安がらせることになります。
解決するにはいろいろな方法があります。真正面からぶつかるだけでは解決策は見つからないのかもしれません。むしろ角度を変えて物事を見るところから、物事の真理は見えてくるものなのかもしれません。眺める角度をもっている人のことを、「応用がきく人」と言います。眺める角度を何方向か使い分けられる人のことを、「できる人」といいます。
話は変わりますが、最近の大雨により九州地方で多くの犠牲者が出ました。近くの川が氾濫して集落が襲われ、何十人という人の命が奪われました。大人の背よりもはるかに高い堤防が決壊して、川の流れはまるで土石流のように重たい土砂を含んで襲ってきました。これなら大丈夫と自信をもって建てられたコンクリートの堤もむなしく意味を失ってしまいました。
まるで昨年の東北大震災でいともたやすくスーパー防波堤を乗り越えた高波を思い出させます。堤の備えは素晴らしいことです。しかし、どんなに高い堤をこしらえたところで、自然の猛威を完全にシャットアウトできないことを、私たちはあの震災で思い知らされました。備えは大切ですが、完全に防ぐことなど不可能なのです。
自然の猛威は完全に防げる、自然には勝てる、というのは間違いです。むしろ、自然には勝てない、と断言した方が正しいと私は思います。そう、だから「逃げる」とか「逃がす」という発想がとても大事なのです。
第一、日本全国がスーパー防波堤のような防御に途方もない予算を使うなんて、ナンセンスだと感じませんか?それじゃあ陸地から波の高さが確認できないじゃないですか(苦笑)。先日の九州の洪水だって、川の防潮堤は水位を確認できませんでした。
水があふれたと知ってから、家の一階部分がまるごと水に呑みこまれるまでの時間は、わずか15分足らずであったそうです。行政は堤に過信するのではなく、決壊を想定して近くに逃げ場所を確保することだって大切だったはずです。
神奈川県内初の津波避難タワーというのが藤沢市の県立湘南海岸公園に先日完成しましたね。海水浴シーズンが始まるのに合わせて建設され、地震発生時に沖にいて逃げ遅れた人の避難を想定しているものです。いわゆる火の見やぐらのような形状のもので、一度に約100人を収容できるそうです。このようなものが、湘南の海沿いの地域にいくつもできれば、それは安心が増えるだろうと感じます。公園の一角でもいい、遊んでいる空き地でもいい、「いざとなったらひとまずあそこに逃げよう」という場所です。お年寄りだって近くにそういう場所があれば必ず助かります。何でも3000万円かかったそうです。いくつ作ったって、防波堤よりは安価だし現実的です。
「逃げる」「逃がす」という、自然の恐さを知った上で今できることをきちんとやっている人は、防波堤さえあれば安心だと言い張ってそればかり主張する人よりは、はるかに「できる人」の成果だと、私は思います。