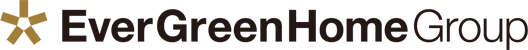食品の表示義務が病的に感じます。
表示をきちんとすることは良いです。けれど、それが一部の人間の責任回避のためにどんどん過剰になっていることが病的に思えます。たとえば豆腐の原材料である、にがり。にがりには精製された粉末状のものと、海水から塩をとる過程で生まれるミネラルを多く含んだ、液状の‘天然にがり’があることはご存じのことと思います。ミネラルのように表示しきれない性格のものは、全てを明確にしなければならない食品表示法では不適合です。なので生産者は自ずと表示しやすい精製にがりを多用するようになり、自然本来のおいしさをもった天然にがりの豆腐を作ることをやめてしまうケースもあります。ミネラルといえども表示できないのだから不適合である、その論理っておかしいですよね。天然にがりの豆腐を製造販売しようと思ったらそのための講習まで受けなければならず、成分を検査にかけてようやく食品としての認定を受けなければならないのです。かかる費用は数十万円・・・。老夫婦でやっている町のおいしい天然にがりのお豆腐屋さんが、このお金をどうやって払えばいいのでしょう?この制度を決めた人は、生活感覚が恐ろしく欠如しているか、さもなくば自らの責任回避だけを考えている人です。
日本の伝統的な保存食、梅干し。その優れた保存能力は‘10年もの’などという銘品がざらにあるほどです。私は梅干しが好きで、いつも塩分10パーセント以下の薄塩の梅干しを地方から取り寄せています。賞味期限を見ました。「え、半年・・・」薄塩とはいえ、この線引きってどこか腑に落ちない感じがしませんか?食品がわるくなる、ならないということよりも、責任回避の匂いの方がプンプンとするから納得がいかないのです。
何か問題が起こった時の責任回避って、まあ必要です。
ただ、今の風潮は病的です。いや、責任回避ですらないかもしれません。責任回避って、責任感のある人がやることですからね。今は皆が責任をとりたくない人達ばかり。だから「責任逃れ」ですね。町の豆腐屋さんを無視した表示規則も、賞味期間は短ければトラブルがないでしょうという短絡的な発想も、どちらも責任逃れに思えます。食
文化を大切にしようだとか、ゴミ問題を真剣に考えよう、などといっておきながら、この国は言っていることとやっていることがまるきり違う責任逃れ大国へと進んでいるかのよう。
先日、増改築のご相談があり、役所に申請前の事前相談に行きました。すると担当係はその設計図を見て「今の建築基準法にのっとった体力壁を設けてください」。それは確かに現行の指針通 りの指示です。しかし、実際は金物補強した側の元になる木の耐久性をはじめ、あらゆる条件、全体のバランスを考えて、はじめてそれは意味のある補強となるのです。「ハイわかりました」と何でもかんでも強い金具を使うことなどできないのです。そこには必ずプロフェッショナルの見識や知恵が必要なのです。相手の一点張りに対して「どうしてですか?」と問うたところで「決まりですから」と言われるでしょうから、暖簾に腕押しです。やはりこれも腑に落ちない感じ。今あるものを大事に使いましょう、という地球規模のマナーに不可欠なのは、臨機応変な見識や知恵であるはず。なのに、実際は局所だけを捉えてのルールの一元化です。
何だかいろいろで、世の中、矛盾していませんか?
※職人至上主義のように受け止められるのは心外なので、職人も悪いところは悪い、と記しておきます。実際、 地場工務店が衰退した原因には、職人が腕と勘だけで仕事をし、世の中の常識から逸脱したデザインをしたり、マナーの欠いたことが大きく関連しています。また、職人の腕(技術)にしても、最後に仕上げの職人が何とかしてくれるだろうとたかをくくり、隠れる部分を雑にしていた、そんな怠慢も一部にあり、そういった大工などは現実に仕事がなくなっています。
私が思うに、時代はもはや、職人=腕、の時代ではなく、より人間性が問われる時代です。自分のしたことにきちんと責任をとれる、そんな「心」をもった人、ですね。まあ、職人だけに限ったことではありませんけどね。